ここ数年、スマートフォンやPCを買い替えるたびに「性能は十分なのに、もうサポートが終わるのか」と感じたことはありませんか。
CPU性能やカメラ画素数といった分かりやすいスペック競争が落ち着く一方で、いまテクノロジー業界では「どれだけ長く、安全に使えるか」が新たな価値基準になりつつあります。GoogleやSamsungが打ち出した7年間のOS・セキュリティアップデート保証は、その象徴的な動きです。
特に日本では、端末価格の高騰や円安の影響により、1台のデバイスをできるだけ長く使いたいというニーズが高まっています。同時に、Windows 10のサポート終了が示したように、ソフトウェア更新が止まることは利便性だけでなく、深刻なセキュリティリスクにも直結します。
本記事では、長期ソフトウェアアップデート時代がもたらす技術的背景や法規制の変化、日本市場特有の事情、そしてリセールバリューや環境負荷といった経済的視点までを整理します。これからのガジェット選びで後悔しないために、知っておくべき判断軸を分かりやすく解説します。
ハードウェア性能競争から製品寿命重視へと移行する背景
2026年を前後して、スマートフォンやPCを中心としたデバイス市場では、明確な価値基準の転換が起きています。かつて購買判断の軸だったCPU性能やカメラ画素数といったハードウェア指標は頭打ちとなり、**日常利用における体感差が生まれにくくなったこと**が大きな要因です。IDCやOmdiaの分析によれば、多くのユーザーにとって近年のミドルレンジ以上の端末は、性能面ですでに「十分すぎる水準」に達しています。
この成熟の中で浮上したのが「どれだけ長く、安全に使えるか」という視点です。象徴的なのが、GoogleとSamsungが相次いで打ち出した**7年間のOSおよびセキュリティアップデート保証**です。これは単なるサポート延長ではなく、製品価値の定義そのものを性能競争から寿命競争へと移行させる強いメッセージでした。欧州連合が施行したエコデザイン指令も、この流れを制度面から後押ししています。
日本市場では、この変化がより切実に受け止められています。総務省系の調査でも示されている通り、端末価格の上昇と円安の影響により、消費者は「頻繁に買い替える前提」から離れつつあります。**高価な端末をできるだけ長く使い続けたいという意識の高まり**が、長期アップデート保証への注目度を一気に引き上げました。
| 従来の価値基準 | 現在の価値基準 |
|---|---|
| CPUクロック・ベンチマーク | OS・セキュリティ更新年数 |
| カメラ画素数 | 修理可能性・部品供給期間 |
| 発売時の新機能 | 長期使用時の安全性 |
さらに、MicrosoftによるWindows 10のサポート終了が示したように、**ソフトウェアの寿命=デバイスの実質寿命**という認識も一般化しました。サポートが切れた瞬間に、性能に問題がなくても「使い続けるリスク」が顕在化することを、多くの個人・企業が経験したのです。これはスマートフォンにもそのまま当てはまります。
こうした背景から、メーカー側も短期的な性能向上より、長期運用を前提とした設計やサポート体制に投資せざるを得なくなっています。**ハードウェア性能競争の終焉は停滞ではなく、価値の再定義**です。スペック表では測れない「時間」という軸が、製品選択の中心に据えられ始めています。
7年間アップデート保証が登場した理由とグローバル動向
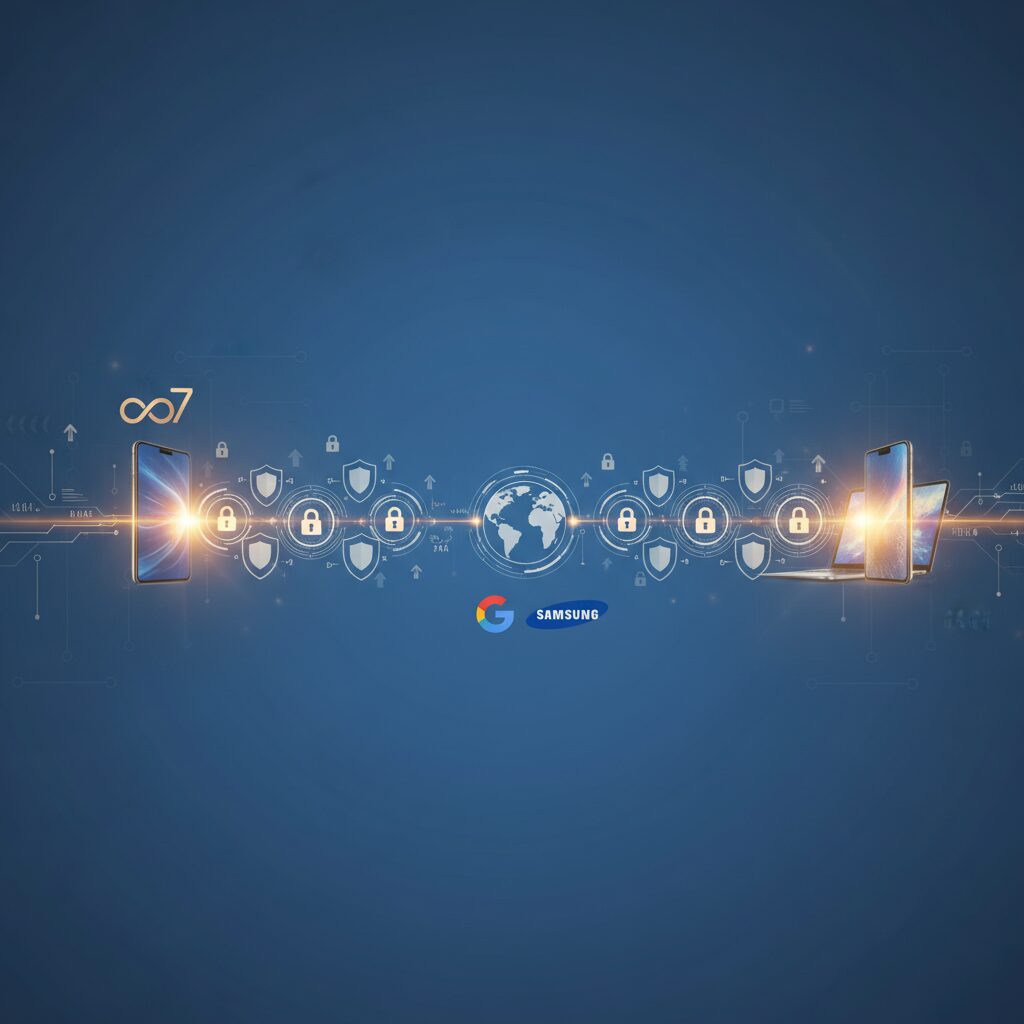
7年間という異例のアップデート保証が登場した背景には、単なるメーカーの差別化戦略を超えた、**グローバル規模での価値基準の転換**があります。2020年代半ば以降、スマートフォン市場ではハードウェア性能の伸びが体感しにくくなり、GoogleやSamsungのようなトップメーカーは「どれだけ長く、安全に使えるか」を競争軸に据え始めました。これは偶然ではなく、世界的な規制と消費者意識の変化が重なった結果です。
最大の外的要因は、欧州連合が主導するエコデザイン規制です。EUは2025年から、スマートフォンに対して販売終了後も長期間のOS更新や修理体制を求めるルールを本格施行しました。欧州委員会の公式資料によれば、**製品寿命の延伸はCO2排出削減に最も効果的な施策の一つ**と位置づけられています。グローバルメーカーにとってEU市場は無視できず、結果としてEU基準が世界標準化していきました。
| 要因 | 内容 | メーカーへの影響 |
|---|---|---|
| EUエコデザイン規制 | 長期OS更新と修理性を義務化 | グローバルでの長期サポート前提設計 |
| 消費者意識の変化 | 高価格化と環境配慮の重視 | 寿命を価値として訴求 |
| 中古・再生市場の拡大 | サポート残年数が価値に直結 | アップデート期間の明確化 |
加えて、調査会社OmdiaやIDCの分析では、スマートフォンの平均使用年数が世界的に伸びていることが指摘されています。**出荷台数が伸び悩む中で、1台あたりの価値を高める方向に産業構造がシフトしている**のです。7年保証は、頻繁な買い替えを前提とした旧来モデルからの決別を象徴しています。
日本市場でもこの流れは無関係ではありません。円安と端末価格の上昇により、「できるだけ長く使いたい」という需要が顕在化しています。総務省関連の白書でも、モバイル端末を3年以上使うユーザーの割合が増加していることが示されています。こうした状況下で、**長期アップデートは安心と資産価値を担保する指標**として受け止められるようになりました。
さらに象徴的なのが、MicrosoftによるWindows 10のサポート終了です。これは多くのユーザーに、ソフトウェアサポートの有無がセキュリティと直結する現実を突きつけました。スマートフォンでも同様に、アップデートが止まること自体がリスクになるという認識が広がり、7年保証の説得力を後押ししています。
このように、7年間アップデート保証は単なる長期サービスではなく、**規制・環境・経済・セキュリティという複数のグローバル潮流が収束した必然の産物**です。世界が「速さ」より「持続」を選び始めたことを示す、極めて象徴的な変化だと言えるでしょう。
EUエコデザイン規制と修理する権利が市場に与える影響
EUエコデザイン規制と修理する権利は、単なる環境政策にとどまらず、スマートフォン市場の競争構造そのものを静かに書き換えつつあります。2025年6月から適用されたEUの新規制では、OSアップデートの最低5年保証や、修理用スペアパーツの7年間供給、さらにユーザーや独立修理業者が修理マニュアルへアクセスできる権利が明文化されました。欧州委員会の発表によれば、これは製品を「買い替えるもの」から「維持し続けるもの」へ転換させるための制度設計です。
この規制が市場に与える最大の影響は、メーカー間の競争軸が性能から寿命と保守性へ移行した点にあります。EU向けだけ仕様を変える非効率を嫌い、AppleやSamsung、Googleといったグローバルメーカーは、設計やサポート体制を世界共通化せざるを得ません。その結果、日本市場でも、修理可能性や長期アップデートが事実上の標準条件になりつつあります。
とくに修理する権利がもたらしたのは、アフター市場の可視化です。Omdiaの分析では、端末出荷台数は減少する一方で、修理、部品供給、リファービッシュ市場の付加価値が拡大すると指摘されています。新品販売だけに依存していたビジネスモデルは、長期的に見て成立しにくくなっています。
| 規制要件 | 内容 | 市場への影響 |
|---|---|---|
| OSアップデート | 販売終了後5年以上 | 長期サポートが購買条件化 |
| 修理用部品供給 | 販売終了後7年間 | 修理・再利用市場の拡大 |
| 修理マニュアル | 一般ユーザーにも提供 | 独立修理業者の参入促進 |
消費者行動にも変化が見られます。欧州の消費者調査では、修理可能性スコアが高い製品ほど購入意向が高まる傾向が報告されており、EUの環境政策シンクタンクECOSも、修理しやすさは価格やブランドと並ぶ評価軸になりつつあると述べています。つまり、修理できること自体が価値として認識され始めています。
この流れは日本にも波及します。端末価格の高騰と円安が続く中で、「壊れたら買い替える」より「直して使い続ける」ほうが合理的という判断が広がっています。EU規制は法的には域外に及びませんが、結果として日本の消費者も、より長寿命で修理前提の製品を選ぶ市場環境に置かれることになります。
EUエコデザイン規制と修理する権利は、メーカーにとってはコスト増要因である一方、差別化の新しい武器にもなります。長く使える設計と透明な修理体制を提示できるかどうかが、これからのガジェット市場で信頼を獲得する分水嶺になりつつあります。
日本のスマホ新法と長期セキュリティアップデートの重要性

日本で2025年末から本格施行されたスマホソフトウェア競争促進法、いわゆるスマホ新法は、一見するとアプリストアや決済手段の自由化を目的とした競争政策に見えますが、実際にはスマートフォンのセキュリティ設計と寿命の考え方に大きな影響を与えています。
とりわけ重要なのが、**長期セキュリティアップデートの価値が、これまで以上に高まっている点**です。新法により、iOSでも外部アプリストアやサイドローディングが容認される方向に進み、Androidと同様にアプリ流通経路が多様化します。これは利便性向上の一方で、プラットフォーマーによる事前審査の網をすり抜けた悪意あるアプリが端末に入り込む余地が広がることを意味します。
Apple自身も公式発表の中で、日本市場向け仕様変更に伴うマルウェアや詐欺アプリ拡散のリスクに言及しています。この環境下では、OSレベルでの脆弱性対策が最後の防衛線となり、**セキュリティパッチが継続的に提供されるかどうかが、端末の安全性を左右する決定要因**になります。
| 観点 | 短期サポート端末 | 長期サポート端末 |
|---|---|---|
| サイドローディング対応後の安全性 | 既知脆弱性が放置されやすい | 月次・定期パッチで封じ込め可能 |
| マルウェア感染時の被害範囲 | 権限昇格や情報窃取のリスク大 | サンドボックス強化で被害を限定 |
| 中古・長期利用の安心感 | サポート切れ=使用自体が危険 | 数年後でも実用・安全水準を維持 |
米国連邦取引委員会やMicrosoftの過去分析によれば、サポート終了OSは攻撃者にとって格好の標的となり、マルウェア感染率が顕著に上昇します。この構造はスマートフォンでも同様で、**OSは動いていてもセキュリティ更新が止まった端末は、事実上の時限爆弾**といえます。
円安と端末価格高騰が続く日本では、一台を長く使う前提で購入判断をするユーザーが増えています。スマホ新法によって自由度が高まるからこそ、長期にわたって最新のセキュリティアップデートが保証されるかどうかは、もはや付加価値ではなく必須条件になりつつあります。
Androidの長期サポートを支える技術革新とGRFの仕組み
Androidが7年間という長期ソフトウェアサポートを実現できるようになった背景には、OS設計思想そのものの大きな転換があります。かつてのAndroidは、新しいOSが出るたびにSoCベンダー、端末メーカー、通信事業者が連鎖的に対応する必要があり、アップデートは高コストかつ不安定でした。その構造を根本から変えたのが、Google主導のアーキテクチャ刷新です。
その第一歩がAndroid 8.0で導入されたProject Trebleでした。OSフレームワークとハードウェア依存部分を明確に分離することで、理論上はハードウェア側を触らずにOSだけを更新できるようになりました。Android開発者向け公式ドキュメントでも、この分離がアップデート高速化の基盤であると説明されています。
| 仕組み | 主な目的 | 長期サポートへの影響 |
|---|---|---|
| Project Treble | OSとベンダー実装の分離 | OS更新の技術的ハードルを低減 |
| GRF | ベンダー実装の仕様固定 | 複数世代にわたるOS更新を制度化 |
しかしTrebleだけでは、3年を超える長期サポートは現実的ではありませんでした。ここで登場したのがGoogle Requirements Freeze、通称GRFです。GRFでは、SoCベンダーが最初に提供したベンダーインターフェースを将来のAndroidバージョンでも再利用することを認め、仕様変更を凍結します。EsperやAndroid Authorityの解説によれば、これによりSoC側の再開発コストが劇的に削減されました。
QualcommのSnapdragon 8 Elite以降を皮切りに、このLongevity GRFが本格導入され、PixelやGalaxyが7年サポートを公約できる技術的・経済的裏付けが整いました。Googleとシリコンベンダーの役割分担を明確に固定することで、長期保守が「例外」ではなく「前提条件」になった点は、Android史上の大きな転換点です。
一方で、この仕組みは万能ではありません。ベンダー実装が固定されるということは、ハードウェア抽象化層が進化しないことを意味します。その結果、新しいAndroidで追加された低レイヤー機能や最新APIの一部が、古い端末では利用できない可能性があります。Google自身も公式情報の中で、OS更新と全機能互換は同義ではないと示唆しています。
それでもGRFの意義は揺るぎません。Androidの長期サポートは、もはやメーカーの努力目標ではなく、設計段階で組み込まれたエコシステムの成果です。ハードウェア進化の速度が鈍化する時代において、この構造的革新こそが、Androidを「長く使えるプラットフォーム」へと押し上げているのです。
7年間使えるかを左右するストレージとバッテリーの現実
7年間のOS・セキュリティアップデートが約束される時代において、実際にその期間を使い切れるかどうかを左右する最大の要因が、ストレージとバッテリーの物理的寿命です。**ソフトウェアが生きていても、ハードウェアが先に限界を迎えれば意味がありません。**
まずストレージです。スマートフォンに使われるNANDフラッシュメモリは、書き込みと消去を繰り返すことで必ず劣化します。米国の半導体研究やAndroid公式技術資料でも示されている通り、この劣化は避けられない物理現象です。特に問題になるのが、低価格モデルに多いeMMCと、近年の主流であるUFSの差です。
eMMCは構造がシンプルで、書き込み負荷を分散するウェアレベリングの効率が低く、数年で体感速度が大きく落ちるケースが多いと報告されています。一方、UFS 3.1や4.0はSSDに近い高度なコントローラを備え、不良ブロック管理やガベージコレクションが洗練されています。MicronやKIOXIAの技術解説でも、**UFSは長期利用を前提とした設計**であることが強調されています。
| 項目 | eMMC 5.1 | UFS 3.1/4.0 |
|---|---|---|
| 主な採用帯 | エントリー〜廉価機 | ミドルハイ〜ハイエンド |
| 通信方式 | 半二重 | 全二重 |
| 長期性能維持 | 低い | 高い |
さらに見落とされがちなのがファイルシステムです。AndroidではF2FSが採用される機種が増えていますが、これはフラッシュメモリ向けに設計され、書き込み回数を抑えることでストレージ寿命を延ばす効果があります。7年運用を考えるなら、UFSかつF2FS対応かどうかは、カタログには載らない重要な判断材料です。
次にバッテリーです。EUのエコデザイン指令や電池メーカーのデータによれば、リチウムイオン電池は500〜800回の充放電で容量が約80%まで低下します。毎日充電するユーザーなら2〜3年で交換時期を迎える計算です。**7年間使う前提では、最低でも2回の交換が現実的**です。
この現実に対し、GoogleやSamsung、Sonyはソフトウェア制御で劣化を遅らせる工夫を進めています。Pixelの電圧制御、Galaxyの80%充電制限、Xperiaのいたわり充電はいずれも、満充電時の高電圧ストレスを避ける仕組みです。Google公式サポートでも、これらはバッテリー寿命を延ばすための設計だと説明されています。
価格やCPU性能よりも、ストレージ規格と電池の扱い方こそが、7年間の快適さを静かに左右します。長期アップデート時代において、この2点を見抜けるかどうかが、賢い選択の分かれ道になります。
アップデート終了が招くセキュリティリスクの実例
ソフトウェアアップデートが終了したデバイスは、見た目や基本動作に問題がなくても、内部では静かにセキュリティリスクが蓄積していきます。特に近年は、攻撃者が「サポート終了端末」を明確に狙い撃ちする傾向が強まっており、アップデート終了は即座に実害へとつながりやすい状況です。
分かりやすい実例が、Windows 10のサポート終了前後に起きた攻撃パターンです。MicrosoftやBitdefenderの分析によれば、サポートが切れたOSでは、新たに発見された脆弱性が修正されないまま恒久的に残り、**マルウェア感染率がサポート中OSより顕著に高くなる**ことが確認されています。
攻撃者はWindows 11向けに公開された修正パッチを解析し、同じ欠陥がWindows 10に残っていないかを調べます。もし存在すれば、それは修正されない“確定した侵入口”となり、ランサムウェアや情報窃取型マルウェアの格好の標的になります。
| 状態 | 脆弱性の扱い | 攻撃者視点 |
|---|---|---|
| サポート中OS | 修正パッチが配布 | 短期間しか使えない |
| サポート終了OS | 修正されない | 長期的に悪用可能 |
この構図はスマートフォンでも同じです。AndroidやiOSでセキュリティアップデートが終了すると、OSやブラウザ、通信スタックに新たな欠陥が見つかっても修正されません。Zimperiumのグローバル調査では、**古いパッチレベルのモバイル端末ほどマルウェア遭遇率が高い**ことが示されています。
特に深刻なのが、ユーザー操作を必要としない「ゼロクリック攻撃」です。メッセージ受信や通信処理だけで侵入が成立するため、注意深い使い方では防げません。実際にAndroidフレームワークの脆弱性が野放しになっている端末では、権限昇格や情報漏えいが確認された事例も報告されています。
また、日本市場特有の事情として、アプリ入手経路の多様化もリスクを増幅させます。公式ストア以外からアプリを導入できる環境では、**OSレベルの防御力が最後の砦**になりますが、アップデートが止まった端末ではその防御が機能しません。
アップデート終了が招く最大の問題は、被害が「静かに進行する」点です。銀行アプリの不正送金、認証情報の抜き取り、業務用アカウントへの侵入など、異変に気づいた時には既に手遅れというケースも珍しくありません。
表面的な動作の快適さとは裏腹に、**アップデートが止まった瞬間からデバイスは防御力を失い続ける**。この現実を理解することが、長期的に安全なデジタル環境を維持する第一歩になります。
日本市場の特殊性と国内メーカーの対応状況
日本市場は、グローバルで進む長期ソフトウェアアップデートの潮流に対して、独自の制約と慣行を抱えています。最大の特徴は、通信キャリアの影響力が依然として強い点です。ドコモ、au、ソフトバンクが販売するキャリア版端末では、OS更新のたびにキャリア独自アプリや通信機能との整合性検証が必要となり、**グローバル版と比べてアップデート配信が遅延、あるいは短期間で終了する傾向**が指摘されています。
米国連邦取引委員会やGoogleの公開資料によれば、Androidのセキュリティパッチは月次提供が前提であるにもかかわらず、キャリア検証を挟む国では数週間から数か月のラグが常態化しています。日本市場はその典型例であり、7年サポートという価値が制度的に活かしきれていない側面があります。
| 観点 | 日本市場の特徴 | グローバル市場 |
|---|---|---|
| 販売チャネル | キャリア主導が中心 | SIMフリー直販が主流 |
| アップデート検証 | キャリア独自検証あり | メーカー主導 |
| 買い替えサイクル | 約2年が前提 | 長期利用が拡大 |
加えて、残価設定型プログラムの普及も日本特有です。2年後の返却を前提とした仕組みは、端末を資産として長く使うという発想と相性が悪く、**長期アップデートの価値が消費者に十分伝わりにくい構造**を生んでいます。端末価格の高騰と円安が進む中でも、制度が購買行動を短期志向に固定している点は見逃せません。
こうした環境下で、国内メーカーは難しい舵取りを迫られています。SonyのXperiaは、カメラやオーディオなど独自ハードウェアへの強いこだわりを維持する一方、OSアップデートは最大3回、セキュリティ更新も5年前後にとどまっています。業界分析では、販売規模が限られる中で7年サポートを実現するためのエンジニアリングコストが重荷になっていると見られています。
SharpのAQUOSは、国内メーカーとして比較的積極的です。最新世代ではOS更新3回、セキュリティ5年を公約し、独自のIGZO OLEDを採用しながらもサポート延長を図っています。これはEUの規制動向を意識しつつ、日本市場でも「長く使える端末」という価値を提示しようとする姿勢の表れと言えます。
FCNTのarrowsは、個人向けよりも法人需要を重視し、Android Enterprise Recommendedへの対応を強化しています。セキュリティ更新期限を明示することで、**業務利用における信頼性を武器に差別化**を図っている点は、日本メーカーの現実的な戦略です。
日本市場では、法規制や商習慣がグローバル標準との摩擦を生み続けています。しかしその一方で、長期アップデートへの消費者意識は確実に高まっています。国内メーカーがこの流れを競争力へ転換できるかどうかは、キャリア依存からの距離感と、サポート期間を価値として訴求できるかにかかっています。
長く使うことで変わるリセールバリューとトータルコスト
スマートフォンを長く使う前提に立つと、購入価格の高さだけで損得を判断するのは危険です。重要になるのがリセールバリューと、数年単位で見たトータルコストです。近年の長期ソフトウェアアップデート保証は、この2つの指標を大きく変えつつあります。
従来、日本市場ではiPhoneの中古価格が突出して高く、Androidは短期間で値崩れするのが常識でした。その背景には、OSアップデートの残存期間が中古価値を左右するという明確な理由があります。ゲオモバイルなど国内大手の買取データでも、最新OSに対応し続ける端末ほど価格が維持されやすい傾向が確認されています。
例えば、Pixel 8やGalaxy S24のように発売時点で7年間のOS・セキュリティ更新が保証されている端末は、3年後に手放したとしても残り4年のサポートが残ります。これは中古購入者にとって大きな安心材料であり、結果として買取価格の下落を抑制します。OmdiaやIDCの分析でも、長期サポートモデルは中古市場での減価が緩やかになると指摘されています。
| 利用年数 | 短期サポート端末 | 長期サポート端末 |
|---|---|---|
| 購入時 | 端末価格は比較的安価 | 端末価格は高め |
| 3年後 | OS更新終了で買取不可に近づく | 更新期間が残り高値を維持 |
| 5年後 | 実質的な使用終了 | バッテリー交換で継続利用可能 |
トータルコストの視点では差はさらに明確です。15万円の端末を2年で買い替える場合、年換算コストは約7.5万円になります。一方、同価格帯の端末を5年以上使い、途中で公式バッテリー交換を1〜2回行った場合、年あたりの負担は大きく下がります。欧州の環境研究機関やFraunhofer研究所の試算でも、使用期間を延ばすことで経済的負担と環境負荷の双方が大幅に低減すると報告されています。
また、日本市場特有の円安と端末価格高騰も見逃せません。新品購入の負担が増す中で、数年後の売却価格まで見据えた選択は家計防衛の観点でも合理的です。長期アップデート保証は、単なる安心材料ではなく、購入から売却までを貫くコスト最適化の仕組みとして機能し始めています。
結果として、「高いが長く使えて高く売れる」端末と、「安いが早く価値を失う」端末の差は、時間が経つほど拡大します。長く使うことで変わるリセールバリューとトータルコストを理解することは、2026年以降のガジェット選びにおいて欠かせない判断軸になっています。
オンデバイスAI時代に求められる次世代の選択基準
オンデバイスAIが本格化する時代において、デバイス選びの基準は大きく書き換えられています。従来はCPU性能やカメラ性能が重視されてきましたが、今後はそれ以上に「AI処理を何年先まで自力でこなせるか」が問われます。IDCによれば、2026年以降のスマートフォン価値はクラウド依存度ではなく、端末内AIの実行能力で差別化されると分析されています。
特に重要なのがNPUの世代とメモリ構成です。オンデバイスAIは音声認識や画像処理だけでなく、個人データを学習するローカルLLMや予測アシスタントへと進化しています。Googleが示す設計指針では、今後のAndroid AI機能は8GB未満のRAMでは段階的に制限される可能性が示唆されています。OSが最新でも、AI機能が使えない端末が生まれる点は見落とせません。
| 観点 | 従来基準 | オンデバイスAI時代 |
|---|---|---|
| 中核性能 | CPU/GPU | NPU性能と世代 |
| メモリ | 快適動作の目安 | 将来AI機能の前提条件 |
| アップデート | OSの新機能 | AIモデル対応可否 |
もう一つの重要な視点がソフトウェア更新とAIの関係性です。GoogleのLongevity GRFによって7年間のOS更新が可能になりましたが、NPUやドライバが固定される以上、将来のAI機能がフルに使える保証はありません。Android Authorityも、7年後のOSは動いても、AI機能は世代差で段階的に切り分けられると指摘しています。
そのため賢い選択とは、単にサポート年数が長い端末を選ぶことではありません。購入時点で余力のあるAI処理性能と十分なRAMを備えているか、そしてメーカーがAI機能の段階的提供について透明性を持っているかが重要です。オンデバイスAI時代のデバイスは、性能の天井が見えている道具ではなく、将来の進化を受け止められる土台であるかどうかで評価されるのです。
参考文献
- Google サポート:Learn when you’ll get software updates on Google Pixel phones
- European Union:New EU rules for durable, energy-efficient and repairable smartphones and tablets start applying
- Microsoft:Ending Support in 2026 – Microsoft Lifecycle
- Android Authority:Here’s how Google is making it easier for Android devices to get 7 years of updates
- Omdia:EU smartphone eco-design regulation is a big challenge to vendors but also necessary change for the industry
- The Japan Times:What will change with Japan’s first attempt at regulating Big Tech?
