スマートフォンの通知に追われ、気づけば一日中集中力が途切れている、そんな感覚を覚えたことはありませんか。
仕事、SNS、ニュース、ショッピングと、私たちのスマホには常に膨大な情報が流れ込み、便利さと引き換えに心身の疲労を蓄積させています。日本では慢性的な疲労を感じる人が多数派となり、通知による注意の分断が生活の質を下げていることも明らかになっています。
こうした状況の中で登場したのが、Google Pixel 10です。Pixel 10は、単なる高性能スマートフォンではなく、AIが通知を自動で整理・要約することで、情報との付き合い方そのものを変えようとしています。
本記事では、Pixel 10がもたらすAI通知整理の仕組みや技術的背景、日本社会への影響、そしてiPhoneとの違いまでを整理しながら、情報疲労から解放されるための新しい選択肢をわかりやすく解説します。ガジェット好きの方はもちろん、日々のデジタル疲れに悩む方にも役立つ内容です。
日本社会で深刻化する情報疲労とスマートフォンの現実
日本社会では今、情報疲労が静かに、しかし確実に深刻化しています。スマートフォンは生活インフラとして完全に定着し、仕事、連絡、決済、娯楽の中心にありますが、その便利さの裏で人々の認知資源は限界に近づいています。**情報疲労は単なる気分の問題ではなく、公衆衛生上のリスクとして捉える段階に入っています。**
一般社団法人日本リカバリー協会が実施した「ココロの体力測定2025」によれば、生産年齢人口の78.5%が疲労を抱えており、約7170万人が慢性的な疲労状態にあると報告されています。特に注目すべきは、41.5%が「高頻度で疲労を感じている」層に該当する点です。この数値は年々上昇しており、日本社会全体の持続性に影を落としています。
| 指標 | 割合 | 推計人数 |
|---|---|---|
| 疲労を抱えている人 | 78.5% | 約7172万人 |
| 高頻度で疲労を感じる人 | 41.5% | 約3786万人 |
この疲労の大きな要因が、スマートフォンから絶え間なく届く通知による注意の断片化です。調査では、高頻度疲労者のうち適切な睡眠時間を確保できている人は43.1%にとどまり、39.7%が中途覚醒に悩まされていました。**枕元に置かれたスマートフォンの通知光や振動が、概日リズムを乱し、回復のための睡眠そのものを侵食している現実が浮き彫りになっています。**
背景には、注意そのものを価値として収益化するアテンション・エコノミーがあります。赤い通知バッジ、不規則に与えられる反応、終わりのないスクロールといった設計は、行動心理学に基づきドーパミン報酬系を刺激するものです。Center for Humane Technologyの提言でも、こうした設計がユーザーの自律性を奪い、「意図しない利用」を常態化させていると指摘されています。
日本ではさらに、即時性を重んじるコミュニケーション文化が状況を悪化させています。LINEの既読機能に象徴されるように、返信の遅れが心理的負担になる環境では、通知を無視するという選択自体がストレスになります。その結果、多くの人が**「見なくてはならない情報」に一日中追い立てられ、常に何かを見逃しているのではないかという不安を抱え続けています。**
かつてはデジタルデトックスが解決策として語られてきましたが、行政手続きや災害情報の受信など、スマートフォンが社会基盤となった現在、完全な遮断は現実的ではありません。情報疲労は個人の意志の弱さではなく、テクノロジーと社会構造が生み出した構造的問題です。この現実を直視することが、次の解決策を考える出発点になります。
アテンション・エコノミーが生む通知過多の構造

私たちのスマートフォンに通知があふれ返る背景には、アテンション・エコノミーという経済構造があります。これは、ユーザーの注意力そのものが価値として取引される仕組みで、プラットフォームやアプリは、いかに長く、頻繁に画面を見てもらうかを競い合っています。
通知は本来、必要な情報を届けるための手段でしたが、現在では注意を奪うための「トリガー」として最適化されています。赤いバッジや振動、音といった刺激は、行動心理学に基づき、反射的な確認行動を引き起こすよう設計されています。
Center for Humane Technologyが指摘するように、現代のアプリ設計はドーパミン報酬系を断続的に刺激する「不規則報酬」の構造を多用しています。いつ重要な通知が来るかわからない状態が続くことで、ユーザーは無意識のうちに端末を何度も確認する習慣に組み込まれていきます。
| 設計要素 | ユーザーへの作用 | 結果として起きること |
|---|---|---|
| 赤い通知バッジ | 危機・未完了感を喚起 | 即時確認の衝動 |
| 不定期な通知配信 | 期待と不安の反復 | 頻繁な端末チェック |
| まとめられない通知 | 注意の分断 | 集中力の低下 |
日本社会では、この構造がさらに強化されています。LINEの既読機能に代表されるように、通知は単なる情報ではなく、即時反応を求める社会的シグナルとして機能しています。返信しないこと自体が人間関係上のリスクになり得るため、ユーザーは通知を無視できません。
結果として、通知は「選べる情報」ではなく「常に対処を迫られるタスク」へと変質しました。一般社団法人日本リカバリー協会の調査で示された注意の断片化や睡眠の質の低下は、個人の自己管理能力の問題ではなく、この経済構造が生み出した必然的な帰結だと言えます。
重要なのは、通知過多が偶発的な問題ではなく、意図的に設計された成果である点です。元Googleのデザイン倫理学者トリスタン・ハリス氏が繰り返し警鐘を鳴らしてきたように、ユーザーの自律性は、最適化の名の下に少しずつ侵食されてきました。
この構造を理解することは、単に通知を減らすテクニック以上の意味を持ちます。なぜ私たちはこんなにも通知に疲れているのか、その根本原因が、注意を資源として消費する経済モデルそのものにあると気づくことが、次の一手を考える出発点になります。
デジタルウェルビーイングは遮断からAI管理の時代へ
これまでデジタルウェルビーイングの主流な考え方は、通知を減らす、使用時間を制限する、端末から物理的に距離を置くといった「遮断」のアプローチでした。確かに短期的な効果はありますが、スマートフォンが社会インフラとなった現在、この方法は現実的な解決策とは言い切れません。行政手続きやキャッシュレス決済、災害情報の受信など、日常生活そのものがデジタルと不可分になっているからです。
その限界を示すかのように、日本リカバリー協会の大規模調査では、生産年齢人口の78.5%が疲労を感じており、その背景に絶え間ない通知による注意の分断があると指摘されています。遮断できない以上、次に求められるのは、人間の意志力に頼らない新しい管理方法です。
ここで登場したのが、AIによる「管理」という発想です。GoogleがPixel 10で提示した方向性は、ユーザーが通知を取捨選択するのではなく、**AIが先回りして情報の重要度を判断し、認知リソースを守る**というものです。これはデジタルウェルビーイングの軸足が、「量を減らす」から「質を高める」へ移行したことを意味します。
| 従来の発想 | AI管理の発想 |
|---|---|
| 通知をオフにする | 通知をAIが整理する |
| 使用時間を制限する | 重要度に応じて提示する |
| 我慢や自己管理が前提 | システムが負荷を肩代わり |
特に注目すべき点は、この管理がリアルタイムかつオンデバイスで行われることです。Googleの公式資料によれば、Pixel 10では通知内容の解析がクラウドを介さず端末内で完結します。これにより、プライバシーを守りながら即座に通知の整理や要約が可能になり、「見るべきかどうか」を一瞬で判断できる環境が整います。
元Googleデザイン倫理学者のトリスタン・ハリス氏が警鐘を鳴らしてきたように、アテンション・エコノミーは人の注意力を奪う構造を持っています。AI管理型のデジタルウェルビーイングは、その構造に真正面から対抗し、**注意力を取り戻すための技術的な防御壁**として機能します。
遮断するのではなく、溺れないように整流する。この転換こそが、情報疲労が臨界点に達した社会における、次のデジタルウェルビーイングの姿だと言えるでしょう。
Pixel 10を支えるTensor G5とオンデバイスAIの進化
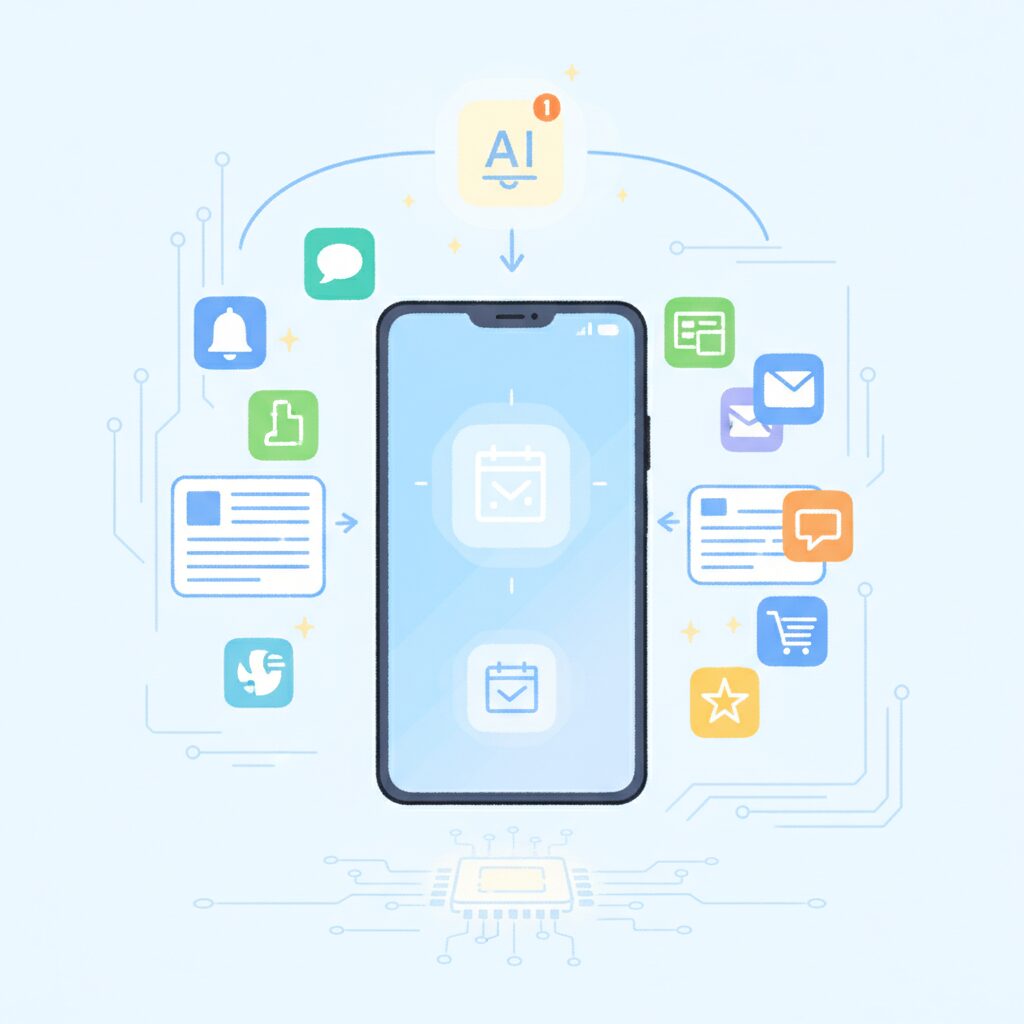
Pixel 10の体験を根底から支えているのが、新開発のGoogle Tensor G5とオンデバイスAIの進化です。今回の世代交代は単なる処理性能の向上ではなく、AIを常時・自然に動かすための基盤づくりという意味合いが色濃く出ています。特に注目すべきは、製造プロセスの刷新とAI専用回路の強化が、ユーザー体験に直結している点です。
Tensor G5は、これまでのSamsung Foundry製プロセスから、TSMCの先端プロセスへと移行した初のTensorチップです。半導体業界の専門家やGoogle公式ブログによれば、この変更により電力効率と熱制御が大幅に改善され、長時間の高負荷処理でも性能低下が起こりにくくなっています。バックグラウンドでAIが常時稼働するPixel 10にとって、発熱と電力効率の改善は不可欠であり、この点がG5最大の技術的ブレークスルーと言えます。
とりわけ重要なのが、TPUを含むNPU性能の強化です。Googleの公開情報では、Tensor G5のAI処理性能は前世代比で最大約60%向上するとされています。これにより、Gemini Nanoのような軽量大規模言語モデルをクラウドに頼らず、端末内で高速に動かすことが可能になりました。通信状況に左右されず、即座に応答するAI体験は、従来のスマートフォンとは一線を画します。
| 項目 | Tensor G4 | Tensor G5 |
|---|---|---|
| 製造プロセス | Samsung Foundry | TSMC先端プロセス |
| AI処理性能 | 従来世代 | 最大約60%向上 |
| AI処理の主軸 | クラウド併用 | オンデバイス中心 |
オンデバイスAI化がもたらす最大の恩恵は、プライバシーとレスポンスの両立です。通知内容や個人的なメッセージは極めてセンシティブですが、Pixel 10では解析処理が端末内で完結します。Googleの公式ドキュメントでも、外部サーバーに送信しない設計が明言されており、プライバシー保護と低レイテンシを同時に実現している点が評価されています。
さらに、通信が不安定な環境でもAI機能が同じ品質で動作する点は見逃せません。地下鉄や災害時など、ネットワークが制限される状況でも、重要な情報判断を端末自身が担えることは、スマートフォンを生活インフラとして使う現代において大きな価値を持ちます。これはクラウドAI依存型の設計では実現が難しい強みです。
Tensor G5とオンデバイスAIの進化は、Pixel 10を単なる高性能端末から、ユーザーの判断を支える知的なデバイスへと押し上げています。処理速度やベンチマークの数字以上に、「いつでも、どこでも、安心して使えるAI」を実現した点こそが、この世代の本質的な進化と言えるでしょう。
Notification Organizerが実現する通知整理の仕組み
Notification Organizerが実現する通知整理の中核には、AIによる文脈理解とリアルタイム処理があります。従来の通知管理は、アプリごとにオン・オフを切り替える静的な設定が中心でしたが、この仕組みでは受信した瞬間に通知内容そのものを解析し、重要度と性質を判断します。ユーザーが事前に細かくルールを作らなくても、通知が自動で整列される点が最大の特徴です。
この判断を担うのが、Pixel 10に搭載されたオンデバイスAIです。Googleの公式ドキュメントによれば、通知のテキスト、送信元、受信頻度、過去のユーザー行動といった複数のシグナルを組み合わせて評価し、緊急性の低い情報はまとめて処理されます。クラウドに送信せず端末内で完結するため、個人メッセージや決済通知といった機微な情報も外部に出ません。プライバシーと即時性を両立させた設計が、この機能の前提条件になっています。
整理の結果、通知は個別に並ぶのではなく、性質ごとにバンドル化されます。例えばセール情報やおすすめ記事は一つのまとまりとして表示され、必要なときだけ展開できます。これにより、ロック画面や通知シェードを開いた瞬間に大量の通知が視界を占領する状況が大幅に減少します。注意資源の研究で知られるスタンフォード大学の行動科学分野でも、人は一度に処理できる情報量が限られていると指摘されており、この設計は認知負荷の軽減に直結します。
| 処理段階 | 従来の通知 | Notification Organizer |
|---|---|---|
| 受信時 | そのまま表示 | AIが即時解析 |
| 分類方法 | アプリ固定 | 内容と文脈で動的分類 |
| 表示形式 | 個別通知が乱立 | カテゴリごとに集約 |
さらに重要なのが学習プロセスです。ユーザーがどの通知をすぐ開き、どれを後回しにするかといった行動は、端末内で継続的に反映されます。特定のアプリや送信者を頻繁に確認していれば、その通知は将来的に優先度が高く扱われます。使えば使うほど、自分の生活リズムに合った通知整理へと近づく仕組みです。
この仕組みは、単なる便利機能にとどまりません。一般社団法人日本リカバリー協会の調査が示すように、日本では慢性的な疲労を感じる人が生産年齢人口の約8割に達しています。その要因の一つが、断続的に注意を奪う通知です。Notification Organizerは通知を減らすのではなく、意味のある形に再構成することで、情報疲労そのものの構造に介入します。
結果としてユーザーは、「今すぐ対応すべきか」「後でまとめて見ればよいか」を一瞬で判断できるようになります。通知に振り回される状態から、通知を主体的に選別する状態へ。Notification Organizerの仕組みは、スマートフォンと人間の関係性を一段階進化させる基盤として機能しています。
AI Summariesによる要約通知と認知負荷の軽減効果
AI Summariesによる要約通知の本質的な価値は、単なる時短ではなく、**人間の認知負荷そのものを構造的に下げる点**にあります。従来の通知体験では、ユーザーは通知を開くたびに「読む・文脈を把握する・重要度を判断する」という一連の認知プロセスを強いられてきました。Pixel 10のAI Summariesは、この負担をAIが肩代わりする設計になっています。
認知心理学では、人が同時に処理できる情報量には限界があるとされ、これをワーキングメモリの制約と呼びます。スタンフォード大学やMITの注意研究でも、断片的な情報に頻繁に晒される環境は、判断精度の低下や精神的疲労を引き起こすことが示されています。**通知を要約して提示する行為は、ワーキングメモリへの入力情報を圧縮する効果**を持ちます。
| 通知体験 | ユーザーの認知行動 | 心理的負荷 |
|---|---|---|
| 従来の通知 | 全文確認・文脈推測・重要度判断 | 高い |
| AI Summaries | 要約確認・要否判断のみ | 低い |
GoogleがPixel 10で採用した要約は、単なる文字数削減ではありません。Gemini Nanoを用いたオンデバイス処理により、**会話の目的や結論といった文脈情報を抽出**する点が特徴です。例えば複数人のグループチャットでも、「議題」「決定事項」「未解決点」が暗黙的に整理され、数行で把握できる形になります。
この設計は、元Googleデザイン倫理学者のTristan Harris氏が提唱してきた「意図しない使用を減らす」という思想とも一致します。通知を開かせること自体を目的とせず、**ユーザーが判断するために必要な最小限の情報だけを前面に出す**という点で、アテンション・エコノミーからの距離を明確に取っています。
日本社会特有の文脈でも、この効果は無視できません。既読プレッシャーや即時返信への同調圧力が強い環境では、通知を開く行為そのものが心理的コストになります。要約通知で内容を把握できれば、**返信タイミングを主体的に選べる余地**が生まれ、注意資源の消耗を防げます。
一般社団法人日本リカバリー協会の調査が示すように、慢性的な疲労状態にある人が多数派となった現在、情報の受け取り方を変えることは公衆衛生的な意味も持ちます。AI Summariesは、テクノロジーが人の注意を奪う存在から、**注意を守る存在へと役割転換する象徴的な機能**だと言えるでしょう。
Magic Cueが変える情報探索と日常行動のサポート
Magic Cueは、従来の検索やアプリ操作の前提を静かに覆す、プロアクティブ型の情報アシスタントです。最大の特徴は、ユーザーが「探しに行く」前に、文脈を理解したAIが必要そうな情報を差し出す点にあります。**情報探索そのものを短縮することで、行動の流れを止めない**という設計思想が貫かれています。
Google公式の解説によれば、Magic Cueは画面上のテキスト、直前の操作履歴、位置情報、時刻といった複数のシグナルをオンデバイスAIで統合解析します。例えば、メッセージアプリで「今日の集合場所どこだっけ?」というやり取りが表示された瞬間、過去のメールにある予約情報やGoogleマップの履歴を横断し、候補地や経路を提示します。**アプリを切り替える行為自体が不要になる**点が、従来の音声アシスタントや検索との決定的な違いです。
この挙動は、人間の認知科学とも整合的です。スタンフォード大学などの研究で知られるように、タスク間の切り替えは集中力を大きく消耗させます。Magic Cueは、この「コンテキスト・スイッチング」をAIが肩代わりすることで、認知的負荷を低減します。結果として、短時間の操作でも判断の質が落ちにくくなります。
| 従来の行動 | Magic Cue利用時 | ユーザー体験の違い |
|---|---|---|
| アプリを記憶して探す | 文脈から自動提示 | 探すストレスが減少 |
| 複数アプリを往復 | 一画面で完結 | 行動が中断されない |
| 手動で情報照合 | AIが関連付け | 判断速度が向上 |
特に日常行動への影響が大きいのは、移動や予定調整の場面です。カレンダーに登録された予定と現在地を照合し、「そろそろ出発した方が良い」という示唆を、検索や通知ではなく行動文脈として提示します。これはMITメディアラボなどが提唱してきたCalm Technologyの考え方とも一致し、**注意を奪わずに行動を支援する**設計だと言えます。
また、すべての処理がTensor G5上で完結する点も重要です。Googleの技術ブログによれば、Magic Cueはクラウドに個人データを送信せずに動作します。これにより、プライバシーを保ちながら即時性の高い提案が可能になります。情報探索の効率化とデジタル・ウェルビーイングを同時に成立させている点は、他社のAI機能と一線を画します。
Magic Cueがもたらす本質的な価値は、便利さ以上に「迷わない時間」を増やすことです。**何を開くべきかを考える前に、次の一手が見える**状態は、忙しい日常において大きな心理的余裕を生み出します。情報が多すぎる時代だからこそ、探さなくていいという体験そのものが、最先端のユーザー価値になりつつあります。
日本語対応とLINE問題に見るローカライズの課題
Pixel 10のAI通知整理は、日本社会の情報疲労に対する有効な処方箋となり得ますが、日本語対応とLINEを巡るローカライズの課題は見過ごせません。特に2026年初頭時点では、Notification OrganizerやAI Summariesを利用するためにシステム言語を英語に設定する必要があり、これは日本の一般ユーザーにとって大きな心理的障壁です。
総務省の調査でも、日本のスマートフォン利用者の多くは端末言語を初期設定から変更しない傾向が示されています。**UI全体が英語になることへの抵抗感は、機能価値そのものよりも普及を左右する要因**になりやすく、これはテクノロジーの性能ではなくローカライズ設計の問題と言えます。
| 観点 | 英語環境 | 日本語環境 |
|---|---|---|
| AI通知要約 | フル対応 | 原則非対応 |
| Notification Organizer | 有効 | 制限あり |
| 主要メッセージアプリ | SMS・WhatsApp中心 | LINE中心 |
問題をさらに複雑にしているのがLINEの存在です。日本では月間利用者数9,500万人規模とされ、日常連絡の基盤インフラになっています。しかしLINEの日本語通知は、文脈依存性が高く、スタンプや省略表現も多用されるため、**英語ベースで訓練されたAIモデルでは意味理解や要約精度が不安定になりやすい**と専門家も指摘しています。
Googleの公式ヘルプでも「AI通知は英語でのみ動作する」と明記されており、日本語LINE通知が正しく要約されない、あるいは分類精度が下がる可能性は否定できません。これは単なる翻訳の問題ではなく、日本語特有の膠着語構造や文脈共有文化への適応が求められる高度な自然言語処理の課題です。
一方で、GoogleはCall Screenや詐欺検出機能など、過去にも時間差で日本語対応を進めてきました。Geminiモデルの多言語性能向上を踏まえると、**2026年中に日本語およびLINE通知への本格対応が行われる可能性は現実的**です。Pixel 10は完成形ではなく、日本市場に最適化される余地を残した“進化途中のデバイス”として評価する視点が重要になります。
iPhoneとの比較で見えるPixel 10の強みと弱み
iPhoneと比較したときに見えてくるPixel 10の最大の強みは、通知という日常的なストレス源に対するアプローチの違いです。AppleはiOS 19で通知要約を強化していますが、その中心は時間指定でまとめて受け取る「Scheduled Summary」にあります。一方、Pixel 10は受信した瞬間にAIが介入し、重要度を判断して整理・要約するリアルタイム志向です。
9to5GoogleやTechRadarのレビューによれば、この即時性は「今見るべきか、後回しでよいか」を判断する認知コストを大きく下げると評価されています。特に仕事中や移動中など、断続的に通知を確認する日本のユーザーにとって、Pixel 10の通知体験は実務的な合理性があります。
| 比較軸 | Pixel 10 | iPhone |
|---|---|---|
| 通知要約のタイミング | 受信時に即時処理 | 指定時間にまとめて配信 |
| 処理方式 | オンデバイスAI | 一部クラウド併用 |
| カスタマイズ性 | 通知単位で柔軟 | 全体設定が中心 |
また、Pixel 10はオンデバイスAIによるプライバシー保護も優位点です。Google公式情報によれば、通知内容の解析はTensor G5上で完結し、外部サーバーに送信されません。個人的なメッセージや決済通知を扱う以上、この設計は安心材料になります。Appleもプライバシー重視を掲げていますが、処理経路の透明性という点ではPixelの説明は具体的です。
一方で弱みも明確です。最大の課題は日本語環境での制約です。Notification OrganizerやAI Summariesは、現時点ではシステム言語を英語に設定する必要があり、日本語通知、とりわけLINEのような国内特化アプリでは本領を発揮できない場面があります。日本市場での実用性という点では、標準設定のまま使えるiPhoneに分があります。
ハードウェア面では評価が分かれます。Pixel 10は無印モデルでも高性能なカメラ構成や120Hz表示を備え、コストパフォーマンスは高いとPhoneArenaは指摘しています。ただし、iPhoneはエコシステム全体の完成度が高く、MacやiPadとの連携を重視するユーザーには依然として魅力的です。
総じて、Pixel 10は情報過多に悩むユーザー向けの攻めた選択肢であり、iPhoneは言語や環境を問わない安定解と言えます。通知体験を根本から変えたい人にはPixel 10が刺さりますが、日本語対応が進むまでは、使いこなす覚悟も同時に求められます。
Material 3 ExpressiveがもたらすUIと心理的変化
Material 3 Expressiveは、単なる見た目の刷新ではなく、ユーザーの心理状態そのものに働きかけるUI設計として位置付けられています。従来のスマートフォンUIは、情報をいかに効率よく詰め込むかに重きが置かれてきましたが、その結果、無意識の緊張や焦燥感を生みやすい構造になっていました。
Material 3 Expressiveでは、この前提が根本から見直されています。色彩、余白、動きといった要素が「操作させるため」ではなく、「安心して使わせるため」に設計されている点が最大の特徴です。Googleの公式デザイン解説でも、ユーザーの感情変化を考慮した表現設計が明言されています。
特に注目すべきは、彩度とコントラストの扱いです。重要な情報だけが自然と目に入り、それ以外は背景に溶け込むよう調整されています。これは注意を奪うUIから、注意を守るUIへの転換を意味します。
| 要素 | 従来UI | Material 3 Expressive |
|---|---|---|
| 色彩設計 | 高コントラスト・強調色中心 | 低刺激なパステルトーン中心 |
| 情報密度 | 常時多情報表示 | 必要時に段階的表示 |
| 操作印象 | 即時反応を促す | 落ち着いた選択を促す |
この設計思想は、行動科学や認知心理学の知見とも一致しています。スタンフォード大学のBJ・フォッグ教授が提唱する行動モデルでは、刺激が強すぎる環境は判断疲れを引き起こすとされていますが、Material 3 Expressiveはその逆を狙ったUIです。
例えば、通知やクイック設定のアニメーションは、派手さよりも一貫性が優先されています。動きはユーザーの注意を引き裂くのではなく、状態遷移を理解させるために使われます。これにより、操作一つひとつが「納得感」を伴う体験へと変わります。
結果として生まれるのが、自己効力感の回復です。UIが穏やかで直感的であるほど、ユーザーは「自分が端末をコントロールしている」と感じやすくなります。これはデジタル疲労の軽減において極めて重要な心理的要素です。
また、Digital Wellbeing周辺のUIでは、数値を突きつけるような表現が抑えられています。利用時間や通知回数といったデータも、責めるようなトーンではなく、状況を静かに示すビジュアルに置き換えられました。Android Policeのレビューでも、この変更が「罪悪感ではなく内省を促す」と評価されています。
Material 3 Expressiveがもたらす最大の変化は、UIが感情のトリガーになる時代の終焉です。触れるたびに焦らされる画面から、安心して委ねられる画面へ。この変化は小さく見えて、日常のストレス総量に確実な差を生み出します。
スマートフォンが生活の背景に溶け込む存在になるために、UIは静かであるべきだという思想。その思想を、具体的な形として実装したのがMaterial 3 Expressiveなのです。
参考文献
- PR TIMES:全国10万人調査から『日本の疲労状況2025』を発表
- Center for Humane Technology:The Attention Economy
- Google Pixel Phone Help:Use AI to manage your notifications
- Google Blog:Stay organized and express yourself with Android 16’s new updates
- 9to5Google:Google Pixel’s notification summaries are better than the iPhone’s, but to what end?
- PhoneArena:iPhone 17 vs Pixel 10: The most heated $799 flagship battle in a decade
